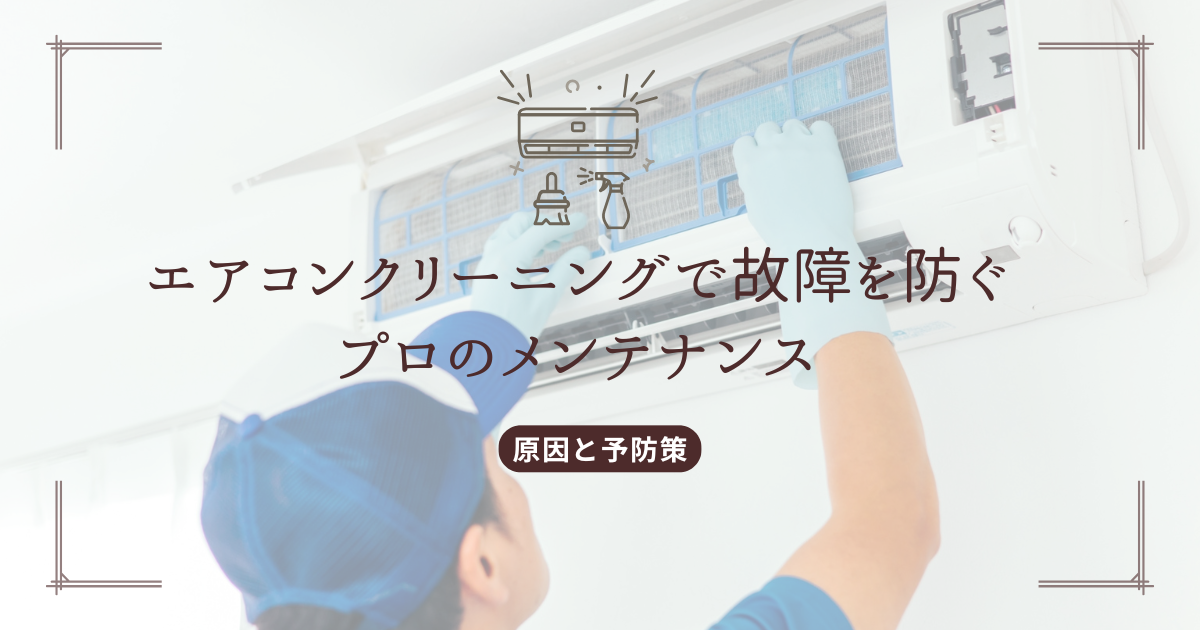「暑い日に、突然エアコンが動かなくなった…!」
「修理費用が高くて、泣きそう…」
エアコンの故障は、突然やってくることがあります。
そして、修理費用は高額になることも…。
真夏や真冬にエアコンが使えないのは、本当に困りますよね。
実は、エアコンの故障は、日頃のメンテナンスや定期的なクリーニングで予防できる場合もあるんです。
この記事では、エアコンが故障する主な原因と、クリーニングや日頃の心がけでできる予防策を詳しく解説します。
- エアコンが故障する主な原因
- エアコンクリーニングが故障予防に効果的な理由
- プロのエアコンクリーニングの内容
- 自分でできる故障予防策
この記事を読めば、あなたもエアコンの故障リスクを減らして安心して快適な夏・冬を過ごせるようになるはず。
エアコンの故障原因と予防策を学び、大切なエアコンを長持ちさせましょう!
エアコンが故障する主な原因

「エアコンって、結構デリケート。どうして故障しちゃうんだろう?」
エアコンが突然動かなくなったり、効きが悪くなったりするのには、いくつかの主な原因が考えられます。代表的なものを知っておくことで、予防にもつながります。
原因1:汚れ(ホコリ、カビなど)
エアコン内部に蓄積するホコリや湿気によるカビなどの「汚れ」は、エアコンの様々な不調を引き起こし、故障につながる最も一般的な原因の一つです。
フィルターの目詰まり
フィルターにホコリがびっしり詰まると、空気の吸い込みが妨げられ、エアコンは通常以上に頑張って空気を吸い込もうとします。この過剰な負荷が、モーターなどの部品に負担をかけ、故障の原因になります。
また、冷暖房の効率も著しく低下し、電気代の無駄遣いにもつながります。
熱交換器の汚れ
空気の温度を実際に変えている重要な部品である熱交換器(フィン)にホコリやカビが付着すると、熱をうまく交換できなくなります。
冷房や暖房の効きが悪くなるだけでなく、エアコンの心臓部であるコンプレッサーなどにも負担がかかり、寿命を縮める可能性があります。
ドレンパンの汚れ
冷房運転時に発生する結露水を受け止める皿の役割をするのがドレンパンです。ドレンパンにホコリやカビ、スライム状の汚れが溜まると、排水経路が詰まり、行き場のなくなった水が室内機からポタポタと漏れ出す「水漏れ」の原因になります。
また、溜まった汚れはカビや雑菌の温床となり、嫌なニオイの原因にもなります。
送風ファンの汚れ
室内に風を送り出すための送風ファンにホコリやカビが付着すると、ファンの回転バランスが崩れて「ブーン」といった異音が発生したり、風を送る力が弱まって風量が低下したりすることがあります。
また、ファンに付着したカビの胞子が風に乗って室内に撒き散らされることにもなり、健康的にも好ましくありません。
原因2:内部部品の劣化
エアコンも機械である以上、長年使用していると構成している様々な部品が経年劣化し、故障することがあります。
冷媒ガス漏れ
エアコン内部を循環し、熱を運ぶ役割をしている冷媒ガスが、配管の劣化による亀裂や接続部の緩みなどから漏れてしまうことがあります。ガスが不足すると、熱をうまく運べなくなり、冷房も暖房も効きが悪くなります。
コンプレッサーの故障
室外機の中にあるコンプレッサーは、冷媒ガスを圧縮して熱交換を可能にする、まさにエアコンの心臓部です。
コンプレッサーが長年の使用による劣化や、過剰な負荷(例えば、汚れによる効率低下など)によって故障してしまうと、エアコンは全く冷えたり暖まったりしなくなります。修理や交換には高額な費用がかかることが多い部品です。
ファンモーターの故障
室内機や室外機でファンを回転させているのがファンモーターです。
ファンモーターが経年劣化や、ファンへの異物混入による負荷などで故障すると、ファンが回らなくなり、風が全く出なくなったり異音が発生したりする原因となります。
原因3:誤った使い方
普段のエアコンの使い方が、知らず知らずのうちに機器に負担をかけ、故障の原因となっていることもあります。
長時間の連続運転
エアコンを何日もつけっぱなしにするなど、極端に長時間の連続運転を行うと、コンプレッサーやファンモーターなどの主要部品に常に負荷がかかり、劣化を早めて故障のリスクを高めます。
適度な休憩(運転停止)を挟んだり、タイマー機能を活用したり、扇風機やサーキュレーターを併用して、エアコンの負担を軽減する工夫が大切です。
頻繁な電源のON/OFF
エアコンは、運転を開始する時に最も大きな電力を消費し、コンプレッサーにも大きな負担がかかります。そのため、部屋を出入りするたびにこまめに電源をON/OFFするのは、かえってエアコンに負荷をかけることになります。
30分程度の短い外出であれば、つけっぱなしにしておくか、設定温度を少し緩める方が、結果的に負担が少なく、電気代も抑えられる場合があります。
設定温度が低すぎる/高すぎる
冷房時に設定温度を極端に低くしたり、暖房時に極端に高くしたりすると、外気温との差が大きくなり、エアコンは目標温度に到達しようと常にフルパワーで稼働し続けることになります。これもコンプレッサーなどに大きな負荷をかけ、故障の原因となり得ます。
快適さを保ちつつ、無理のない適切な温度設定を心がけることが重要です。
原因4:室外機の環境
見落としがちですが、屋外に設置されている室外機の周辺環境も、エアコンの効率や寿命に影響を与え、故障の原因となることがあります。
直射日光
室外機本体に長時間、強い直射日光が当たると、内部の温度が上昇し熱交換の効率が悪くなります。結果としてエアコンの効きが悪くなったり、余計な電力を消費したりします。
可能であれば、よしずやすだれ、専用の日よけカバーなどで日陰を作る工夫をすると良いでしょう。(ただし、空気の通り道を塞がないように注意が必要です。)
風通しの悪さ
室外機の周りに物がたくさん置かれていたり、雑草が生い茂っていたりすると、空気の流れが妨げられ、熱交換がスムーズに行えなくなります。
これもエアコンの効率低下や負担増加につながるため、室外機の周囲は常に整理整頓し、風通しが良い状態を保つようにしましょう。
周辺の障害物
室外機の吸込口や吹出口が、壁や塀、植木などで近すぎたり、塞がれていたりすると、空気の循環が著しく悪化します。これにより、エアコンの効率が大幅に低下し、機器に大きな負担がかかって故障の原因となります。
設置場所の基準(通常、前後左右に必要なスペースが指定されています)を守り、障害物がないか定期的に確認しましょう。
エアコンクリーニングで故障を予防

「エアコンクリーニングって、きれいになるだけじゃなくて、故障予防にもなるって本当?」
定期的なエアコンクリーニングは、エアコンを快適に使うだけでなく、故障のリスクを減らし、機器を長持ちさせるためにも非常に効果的なメンテナンスなのです。
汚れを除去してエアコンへの負荷を軽減
エアコンクリーニングでは、フィルターはもちろん、内部の熱交換器やドレンパン、送風ファンなどに溜まったホコリやカビ、その他の汚れを徹底的に除去します。これらの汚れは、空気の流れを妨げたり、熱交換の効率を悪化させたりして、エアコン本体に余計な負荷をかけています。
クリーニングによってこれらの汚れを取り除くことで、エアコン各部への負担が軽減され、結果的に故障のリスクを減らすことにつながります。
プロの目で故障の兆候を早期発見
エアコンクリーニングを専門に行うプロの業者は、様々な機種のエアコンの構造や仕組みに精通しています。
クリーニング作業中に、部品の劣化具合や異音、水漏れの痕跡など、故障につながる可能性のある細かな兆候に気づいてくれることがあります。早期に問題を発見できれば、本格的な故障に至る前に対処できる可能性が高まります。
定期的なクリーニングでエアコンを長持ち
どんな機械製品も、定期的なメンテナンスによってその寿命を延ばすことができます。エアコンも例外ではありません。
定期的に内部の汚れを取り除き、清潔で効率の良い状態を保つことは、エアコン本体への負担を減らし、部品の劣化を遅らせることにつながります。結果として、エアコンをより長く、快適に使い続けることができるのです。
クリーニングによる電気代節約効果については、下記の記事で詳しく解説しています。
プロのエアコンクリーニングって何をしてくれる?
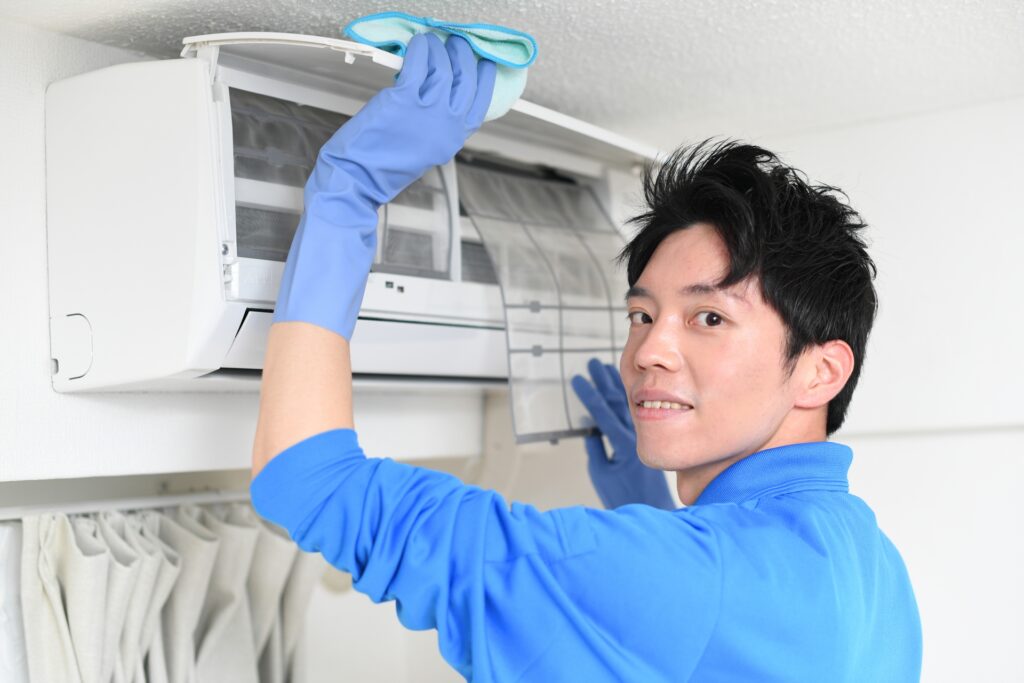
「業者さんに頼むと、具体的にどんな掃除をしてくれるの?」
プロのエアコンクリーニングは、自分で行う掃除とは異なり専門的な知識と道具を用いて、エアコン内部の見えない部分まで徹底的に洗浄してくれるのが特徴です。主な作業内容は以下の通りです。
分解洗浄。内部部品を取り外して洗浄
エアコンの前面カバーやフィルターなどを取り外し、必要に応じてさらに内部の部品(送風ファンなど)を分解します。普段のお手入れでは手が届かない、エアコンの心臓部ともいえる熱交換器(フィン)や、風を送り出すための送風ファンなどを露出させ、直接洗浄できる状態にします。
高圧洗浄。専用機材で汚れを強力に洗い流す
露出させた熱交換器や送風ファンやドレンパンなどに専用の洗剤を塗布した後、高圧洗浄機を使って大量の水で勢いよく洗い流します。これにより、こびりついたホコリやカビ、油汚れなどを根本から除去します。
周囲が汚れないように、エアコン全体を専用のカバーで覆って作業を行うのが一般的です。
防カビ・抗菌コート
洗浄後、きれいになった熱交換器や内部部品に、専用の防カビ剤や抗菌剤をコーティングするサービスを提供している業者もあります。これにより、クリーニング後のカビや雑菌の再繁殖を一定期間抑制する効果が期待できます。
多くの場合、これはオプションサービス(追加料金)となっています。
動作確認。正常な動作を最終チェック
洗浄・乾燥・組み立てが完了した後、実際にエアコンを運転させ、異音や異臭がないか、冷暖房が正常に機能するかなどを確認します。
問題なく動作することを確認して、作業完了となります。
故障診断。作業中の簡易的な状態チェック
熟練した作業員の場合、分解や洗浄の過程で、部品の劣化具合や異音の兆候など、故障につながる可能性のある簡単なチェックを行ってくれることもあります。
ただし、これは本格的な故障診断ではなく、あくまでクリーニング作業中の気づきの範囲内であることが多いです。
自分でできる故障予防策

「エアコンが壊れる前に、自分で何かできることはないかな?」
専門業者によるクリーニングも大切ですが、日々の使い方やちょっとしたお手入れで、エアコンの故障リスクを減らすことができます。
こまめなフィルター掃除
エアコンのフィルターは、空気中のホコリをキャッチする最初の関門です。
フィルターにホコリが溜まると、空気の吸い込みが悪くなり、エアコン本体に大きな負荷がかかります。これが故障の原因になることも。
2週間に1回を目安に、掃除機でホコリを吸ったり、水洗いしたりして、常にきれいな状態を保つように心がけましょう。
室外機の周辺を清潔に
屋外にある室外機の周りに物が置かれていたり、雑草が生い茂っていたりすると、空気の流れが妨げられ、熱交換の効率が悪くなります。これもエアコンへの負担増につながります。
室外機の周囲は常に整理整頓し、十分なスペースを確保して、風通しを良くしておくことが大切です。
適切な温度設定
冷房時に設定温度を極端に低くしたり、暖房時に極端に高くしたりすると、エアコンは常にフルパワーで稼働しようとし、コンプレッサーなどの部品に大きな負担がかかります。
快適さを損なわない範囲で外気温との差が大きくなりすぎない、無理のない適切な温度設定を心がけることも故障予防につながります。
長時間の連続運転を避ける
エアコンを何日もつけっぱなしにするような極端な連続運転は、機器に常に負荷をかけることになり、部品の劣化を早める可能性があります。
タイマー機能を活用したり、時には窓を開けて換気したり、扇風機やサーキュレーターを併用したりして、エアコンが連続して稼働する時間を意識的に減らす工夫も有効です。
異音や異臭に注意する
エアコンの運転中に、普段とは違う「ガタガタ」「キーキー」といった音(異音)がしたり、「カビ臭い」「焦げ臭い」といったニオイ(異臭)がしたりする場合は、何らかの異常が発生しているサインかもしれません。
そのまま使い続けると状態が悪化したり、危険が伴ったりすることもあるため、専門業者に点検を依頼しましょう。早期発見・早期対処が重要です。
まとめ
エアコンの突然の故障は避けたいものですが、多くは日頃の使い方やお手入れ次第で予防できる可能性があります。汚れの蓄積、部品の劣化、誤った使い方、設置環境の問題など、故障につながる原因を知ることが、まず第一歩です。
そして、自分でできるこまめなフィルター掃除や室外機周りのケア、適切な温度設定といった日頃の心がけが非常に重要になります。これだけでも、エアコンへの負担を減らし、故障のリスクを低減させることができます。
さらに、自分では手の届かない内部の汚れを徹底的に除去し、故障の兆候を早期に発見するためにも、定期的なプロによるエアコンクリーニングは有効な手段です。
日々の簡単なメンテナンスと、適切な時期のプロによるクリーニングを上手に組み合わせることで、故障の心配を減らせます。
エアコンを長持ちさせ、一年中快適な空気の中で過ごす「故障知らずの快適エアコンライフ」を実現しましょう!