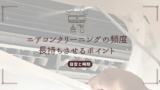「エアコンのフィルター掃除、面倒だな…」
「ちょっとくらい汚れていても、大丈夫でしょ…」
そう思って、エアコンフィルターの掃除を怠っていませんか?
実は、エアコンフィルターは、カビが繁殖しやすい場所なんです。
そして、カビを放置すると、健康被害のリスクも…!
エアコンから吹き出す風に乗って、カビの胞子が部屋中に広がり、アレルギー性鼻炎や喘息、アトピー性皮膚炎などを引き起こす可能性があります。
この記事では、エアコンフィルターのカビ対策について解説します。
- エアコンフィルターにカビが生える原因
- エアコンフィルターのカビ対策(簡単お手入れ方法)
- エアコンフィルターにおすすめの便利グッズ
- エアコンフィルター掃除の頻度と時期
この記事を読めば、あなたもエアコンフィルターのカビ対策がバッチリできるようになるはず。
エアコンフィルターを清潔に保ち、快適な空間を手に入れましょう!
エアコンフィルターのカビの原因とメカニズム

「エアコンのフィルター、気づいたらカビが生えてる…どうして?」
エアコンフィルターは、室内の空気をきれいにするための重要な部品ですが、残念ながらカビが繁殖しやすい場所でもあります。ここでは、なぜフィルターにカビが生えてしまうのか、その主な原因とメカニズムを解説します。
原因1:ホコリ
エアコンは、部屋の空気を吸い込んで、冷やしたり暖めたりしてから吹き出す仕組みです。その際、空気中に漂うホコリも一緒に吸い込んでしまいます。
ホコリはカビの栄養源
吸い込まれたホコリは、まずフィルターに付着します。このホコリには、人の皮脂や食べ物のカスなども含まれており、これがカビにとって格好の栄養源となってしまうのです。また、ホコリ自体にカビの胞子が付着していることもあります。
フィルターの目詰まりの原因にも
フィルターにホコリが大量に溜まると、空気の通り道が塞がれて目詰まりを起こします。これにより、エアコンの効きが悪くなったり、余計な電力を消費したりするだけでなく、内部の湿度も上がりやすくなり、さらにカビが繁殖しやすい環境を作ってしまいます。
原因2:湿度
エアコン内部の湿度の高さも、カビ発生の大きな要因です。
冷房・除湿運転で結露が発生
特に冷房や除湿運転を行うと、エアコン内部にある熱交換器(フィン)という部品が急激に冷やされます。これにより、空気中の水分が冷やされて結露し、水滴となって内部に付着します。
カビは湿度を好む
カビは湿った環境を非常に好みます。エアコン内部に結露によって水分が存在し、湿度が高い状態(特に湿度70%以上)が続くと、フィルターや内部の部品でカビが活発に繁殖しやすくなります。
原因3:温度
カビの繁殖には、湿度だけでなく温度も関係しています。
20℃~30℃でカビは活発に
多くの種類のカビは、温度が20℃から30℃程度の、人間にとっても比較的過ごしやすい温度帯で最も活発に増殖します。
エアコン使用中の温度に注意
エアコンを使用している間、特に冷房運転中は、エアコン内部がこのカビの好む温度帯になることが多くなります。設定温度を低くしすぎると、室内との温度差で結露も発生しやすくなるため、カビにとってはさらに好都合な環境が整ってしまいます。
カビが繁殖しやすい条件
これらの条件が揃うと、エアコンフィルターでカビが繁殖しやすくなります。
特に、梅雨時や夏場は、カビが繁殖しやすい条件が揃いやすいため、注意が必要です。
エアコンフィルターのカビ対策!簡単お手入れ方法

「フィルターのカビ、何とかしたい!簡単にできる対策はないかな?」
エアコンフィルターにカビが生えるのを防ぐ、または発生してしまったカビを取り除くためには、定期的で正しいお手入れが重要です。
ここでは、ご家庭で簡単にできるフィルターのお手入れ方法をご紹介します。
用意するもの
まず、フィルター掃除を始める前に、以下の道具を準備しましょう。
掃除機
フィルター表面についた大きなホコリを吸い取るのに使います。ノズルがブラシ状になっているものや、細い隙間ノズルがあると、より効率的にホコリを除去できます。
ハンディタイプでももちろんOKです。
古歯ブラシ
フィルターの網目に入り込んだ細かいホコリや、水洗いする際に汚れを優しくこすり落とすのに役立ちます。わざわざ新しいものを買う必要はなく、使い古した歯ブラシで十分です。
中性洗剤 (必要な場合)
ホコリだけでなく、油汚れなどが付着していて水洗いだけでは落ちない場合に使います。必ず食器用などの中性洗剤を選んでください。
アルカリ性や酸性の洗剤、カビ取り剤を含む塩素系漂白剤は、フィルターの素材を傷めたり変質させたりする可能性があるので、絶対に使用しないでください。
バケツ (必要な場合)
フィルターのサイズによっては、洗面台で洗いにくい場合があります。また、洗剤を使って浸け置き洗いをする際には、バケツがあると便利です。
ゴム手袋・マスク (必要な場合)
洗剤を使う際に手が荒れるのを防いだり、カビやホコリを吸い込んだりするのを防ぐために、必要に応じてゴム手袋やマスクを着用しましょう。特にカビが見られる場合は、胞子を吸い込まないためにもマスクの着用をおすすめします。
手順1:フィルターを取り外す
安全に正しく取り外す
まず、安全確保のために必ずエアコンの電源プラグをコンセントから抜きましょう。次に、ご自宅のエアコンの取扱説明書を確認し、フィルターの正しい取り外し方を確認します。機種によってロックの解除方法などが異なります。
フィルターを外す際には、溜まっていたホコリが舞い散ることがあるので、床に新聞紙を敷いたり、マスクを着用したりしておくと安心です。
手順2:掃除機でホコリを吸い取る
大きなホコリをまず除去
取り外したフィルターの、ホコリが付着している表面側から掃除機をかけます。フィルターの網目に沿って、ノズルをゆっくりと動かしながら、大きなホコリを丁寧に吸い取りましょう。
このひと手間で、後の水洗いが楽になります。
手順3:水洗いする
裏から水流で汚れを押し出す
掃除機で取りきれなかった細かいホコリや汚れを水で洗い流します。この時、必ずフィルターの裏側(ホコリが付いていない面)からシャワーなどの水を当ててください。こうすることで、網目に詰まったホコリが水の勢いで効率よく押し出されます。
もし油汚れなどが付いていて落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤をつけた古歯ブラシで優しくこすり洗いします。洗剤を使った場合は、泡が完全になくなるまで、念入りに水で洗い流しましょう。
手順4:しっかり乾燥させる
カビ防止のため完全に乾燥
洗い終わったフィルターは、カビの再繁殖を防ぐために、完全に乾燥させることが非常に重要です。タオルなどで優しく水気を拭き取った後、直射日光を避け、風通しの良い場所で陰干ししましょう。ドライヤーの熱風を当てるのは、フィルターが変形する可能性があるので避けてください。
完全に乾いたことを確認してから、エアコンに元通り取り付けます。
カビがひどい場合の対処法
フィルターに黒い点々としたカビが目立つ場合や、中性洗剤で洗ってもなかなか落ちない場合は、以下の方法を試してみてください。
ただし、これらの方法はフィルターの素材によっては適さない場合もあるため、取扱説明書を確認するか、目立たない場所で試してから行うようにしましょう。
酸素系漂白剤を使う
酸素系漂白剤(粉末タイプが一般的)は、除菌・漂白効果があり、フィルターのカビ除去にも有効です。バケツなどに40℃~50℃くらいのぬるま湯を張り、規定量の酸素系漂白剤をよく溶かしてから、フィルターを30分~1時間程度浸け置きします。時間が経ったら、フィルターを取り出して流水でよくすすぎ、完全に乾燥させてください。
重曹を使う
研磨効果と弱アルカリ性の性質を持つ重曹も、カビ取りに利用できます。重曹に少しずつ水を加えながら練り、ペースト状にしたものを、カビが気になる部分に直接塗りつけます。そのまま10分程度放置した後、古歯ブラシなどで優しくこすり落とします。その後、水で十分に洗い流し、しっかりと乾燥させましょう。
エアコンフィルターのカビ対策におすすめ!便利グッズ

「フィルター掃除、もっと楽に、効果的にできないかな?」
ここでは、エアコンフィルターのカビ対策や日々のお手入れを、より簡単・便利にしてくれるおすすめグッズをご紹介します。
エアコンフィルター掃除用ブラシ
特徴
エアコンフィルターの細かい網目に詰まったホコリを効率よくかき出すために設計された専用ブラシです。掃除機のノズルでは届きにくい部分のホコリ除去に役立ちます。様々な形状や硬さのものがあり、中には静電気を利用してホコリを吸着するタイプもあります。
選び方
ブラシの硬さや形状が、ご自宅のエアコンフィルターの素材や網目の大きさに合っているかを確認して選びましょう。フィルターを傷つけない柔らかめの素材がおすすめです。
エアコンフィルター用洗剤
特徴
エアコンフィルターの洗浄を目的とした専用の洗剤も市販されています。通常のホコリ汚れだけでなく、油汚れなどに効果的な成分が配合されていたり、洗浄と同時に防カビや除菌効果が期待できるものもあります。
多くは中性ですが、製品によっては弱アルカリ性のものも存在します。
選び方
フィルターの素材(プラスチックなど)に使用可能か、落としたい汚れの種類(ホコリ、油汚れなど)に適しているかを確認して選びましょう。防カビ・除菌効果の有無もチェックポイントです。
防カビ・抗菌スプレー(フィルター用)
特徴
清潔にしたフィルターにスプレーすることで、カビや雑菌の繁殖を一定期間抑制する効果が期待できるスプレーです。フィルター掃除の仕上げに使うことで、きれいな状態をより長持ちさせるのに役立ちます。
使い方
フィルターを洗浄し、完全に乾燥させた後に、フィルター全体に均一にスプレーします。使用量や乾燥時間は、製品の指示に従ってください。
防カビスプレー(エアコン内部用)
特徴
こちらはエアコンの吹き出し口など、内部に向けてスプレーすることで、カビの発生を抑制する効果を謳った製品です。フィルターだけでなく、エアコン内部のカビが気になる場合に補助的に使用します。
使い方
製品によって使用方法や対象箇所が異なります。誤った使い方をすると故障の原因にもなりかねないので、必ずエアコン本体及びスプレー製品の取扱説明書をよく読み、指示に従って正しく使用してください。
使い捨てフィルター
特徴
元々エアコンについているフィルターの上に、さらに重ねて取り付ける使い捨てタイプのフィルターシートです。空気中のホコリをこの使い捨てフィルターでキャッチするため、純正フィルター本体の汚れを軽減できます。
使い方
ご自宅のエアコンフィルターのサイズに合わせてシートをカットし、純正フィルターの外側(空気の吸い込み側)に貼り付けたり、被せたりして使用します。汚れてきたら、シートを剥がして新しいものに交換するだけなので、フィルターの水洗いなどの手間を大幅に省くことができます。
エアコンフィルター掃除の頻度と時期

「エアコンフィルターの掃除って、どのくらいのペースで、いつやるのがベストなの?」
エアコンフィルターを清潔に保つことは、カビ対策だけでなく、エアコンの効率維持や電気代節約のためにも重要です。
理想的な頻度:2週間に1回
こまめな掃除が大切
エアコンフィルター掃除の理想的な頻度は、一般的に「2週間に1回」と言われています。
フィルターは空気中のホコリをキャッチする役割があるため、思った以上に早く汚れていきます。特にエアコンを毎日使用する夏や冬のシーズン中は、この頻度を目安にこまめに掃除をすることで、ホコリの蓄積やカビの繁殖を効果的に防ぐことができます。
使用状況で調整
ペットを飼っていて毛が舞いやすい環境や、アレルギー体質のご家族がいるご家庭など、より室内の空気環境に気を配りたい場合は、週に1回など、さらに頻度を上げて掃除を行うのがおすすめです。
自分のライフスタイルや使用状況に合わせて調整しましょう。
時期:冷暖房シーズン前、シーズン中、シーズン後
フィルター掃除を行うのに特に効果的なタイミングがあります。
シーズン前の掃除
本格的に冷房や暖房を使い始める前には、必ず一度フィルターを掃除しましょう。オフシーズン中に溜まったホコリや、もし発生していればカビなどを取り除き、きれいな状態でシーズンをスタートさせることができます。
シーズン中の掃除
冷房や暖房を頻繁に使うシーズン中は、先ほど述べたように「2週間に1回」程度の頻度で、こまめにフィルター掃除を続けることが理想です。これにより、エアコンの効率低下を防ぎ、清潔な空気を保つことができます。
シーズン後の掃除
冷房や暖房を使わなくなるシーズン終わりにも、一度フィルターを掃除しておくことをおすすめします。
シーズン中に吸い込んだホコリや、場合によっては発生したカビの胞子などをきれいに取り除いておくことで、汚れを長期間放置せず、次のシーズンに気持ちよくエアコンを使い始めることができます。
エアコン掃除の適切な頻度については、下記の記事で詳しく解説しています。
エアコン内部のカビ対策
フィルターをきれいにしても、エアコンからカビ臭いニオイがしたり、吹き出し口の奥に黒い点々が見えたりする場合は、エアコン内部(熱交換器や送風ファンなど)にカビが繁殖している可能性があります。これらの部分は構造が複雑で、自分で分解して掃除することは故障や感電のリスクが非常に高いため、絶対にやめましょう。
エアコン内部のカビを根本から除去するには、専門的な知識と機材を持つプロのエアコンクリーニング業者に依頼するのが最も安全かつ効果的です。
また、内部にカビを発生させないための日頃からの予防策も大切です。冷房を使った後は送風運転(または内部クリーン機能)で内部を乾燥させる、定期的に部屋の換気を行うといった習慣を心がけることで、カビが繁殖しにくい環境を作るようにしましょう。
まとめ
エアコンのフィルターは、ホコリが溜まりやすく、湿気と温度の条件が揃うと、カビにとって格好の繁殖場所となってしまいます。フィルターに発生したカビをそのままにしておくと、エアコンを使うたびにカビの胞子を部屋中に撒き散らすことになり、健康に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。
だからこそ、今回ご紹介したような簡単なお手入れ方法で、フィルターをこまめに掃除することが、エアコンのカビ対策の基本であり、非常に重要なのです。
掃除機でのホコリ取りや水洗い、そして時には便利グッズの力も借りながら、ぜひ定期的なフィルター掃除を習慣にしてみてください。
そして、もしフィルターをきれいにしてもカビ臭さが取れない、内部の汚れが気になる、という場合には、無理せずプロのエアコンクリーニング業者に相談することも検討しましょう。
適切な対策で、カビの心配のない清潔なエアコンを保ち、快適な毎日を送りましょう!